特定技能外国人の日本語レベル・日本語能力(日本語能力試験)について行政書士が解説

2022/6/17執筆
2019年4月から運用が開始された新しい在留資格「特定技能*」ですが、この制度で就労する外国人労働者はどの程度の日本語能力を持っているのか、雇用する側としては気になる点だと思います。
そこで、特定技能外国人の日本語レベルについて、現役行政書士が解説します。
*特定技能には「1号」と「2号」がありますが、ここでは便宜上「特定技能1号」のことを「特定技能」と表現します。
「特定技能」へのルートによって日本語能力は異なる
ひと口に「特定技能外国人」と言っても、その経歴は様々ですが、次のようなルートが考えられます。
- 今まで日本に来たことがなく、「特定技能試験」と「日本語試験」に合格してから入国するルート。この場合、日本語能力は「特定技能」に求められるミニマルなレベルを満たしている程度であると考えられます。
- 「技能実習生」として3年~5年の間、日本で就労した後に「特定技能」へ移行するルート。この場合、日本語試験が免除されます。これは、移行可能な要件を備えた元実習生とは、「技能実習評価試験」を合格していることが前提ですので、日本語で出題されたある程度の専門知識を要する試験に合格していることで、日本語能力が担保されているというわけです(出題文の漢字にルビ振りあり)。
- 「留学」や「家族滞在」などで日本に在留していた外国人が「特定技能試験」や「日本語試験」に合格して、在留資格を変更するルート。滞在年数にもよりますが、すでに日本で生活経験があるので、実践的な日本語力をある程度身に着けているものと思われます。
そして、ここでいう「日本語試験に合格」というのは「特定技能の在留資格が許可されるために求められる日本語能力」であるJLPT(日本語能力試験)N4又はJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)の合格基準点である200点(250点満点)を上回っているか、で判断されます。
JLPT N4やJFT-BASICのレベルとは?(特定技能外国人の日本語能力試験・日本語基礎テスト)
JLPT N4やJFT-Basicに合格するには、どのくらいの能力が必要なのでしょうか。それぞれ解説します。
特定技能外国人の日本語能力試験 JLPT N4とは
JLPTは、次のようにレベルの目安を公表しています。

特定技能外国人の日本語基礎テスト JFT-Basicとは
また、JFT-Basicでは、テストの目的を
『主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定すること』としています。
このような表現だと、「カタコト」程度なのではないか、と思いがちですが、これらのレベルをCEFR(外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠「セファール」)で表すと「A2」であり、日本人にとっての英検準2級がこれに相当します。英検準2級といえば、高校中級程度(2級で高校卒業程度)です。そう考えると、カタコト以上のレベルであることがわかります。


特定技能外国人を雇用した場合「母国語による支援」が必要な理由
「なんだ、わりとレベル高いのでは?なぜ、母国語による支援が必要なの?」と思われるかもしれません。しかし、(日本人外国人を問わずに求められることではありますが)「特定技能」においては、適正な雇用であることが大前提であり、雇用条件について労働者がしっかりと理解していることが必要なのですが、では、雇用条件書を見せられて、果たして内容を余すことなく理解できるでしょうか。
「変形労働時間制」
「割増賃金率、法定超月60時間以内の場合は…」
「労使協定に基づく賃金支払時の控除」など
日本人でもあまり正確に理解しないまま雇用契約を交わしている人も多いと思われます。
そして、N4で網羅している漢字は300字程度で、小学校中学年レベルであるため、読み書きに関しては、特に非漢字圏出身者の場合は理解が難しいことから、「特定技能外国人が十分に理解できる言語にて」雇用条件に関わる重要事項についてのガイダンスや不当な扱いを受けていないか確認するための定期面談を行うこと、とされており、実務的には「母国語による」支援を行うことが義務付けられているのです。
特定技能外国人に母国語支援を行いつつも最低限の日本語レベルが必要な理由
逆に、「母国語での支援体制を整えることを義務付けているなら、日本語能力はなくてもいいじゃないか」という意見もあるかと思います。しかし、やはり、建設業や機械操作などにおいては、安全衛生確保の観点から、現場にいる他従業員が危険回避のためのとっさの指示を日本語で出した時に理解できなければ事故につながりかねませんし、介護や外食業においては、相手があってのビジネスですので、最低ラインとして、この日本語レベルを求めることは妥当であると言えます。
結論:特定技能外国人は最低限の日本語レベルがある&職場では更なる日本語能力向上を支援していきましょう
特定技能の在留資格の要件を満たしている外国人は、日常生活において、ある程度のコミュニケーションは可能であると言えるレベルの日本語力を身に着けていると言えます。
読み書きの能力については、出身国の言語によって大きく左右されることが想定されます。
そして、日常の生活場面において十分なコミュニケーションが取れるからといって、日本語学習の継続をそのまま外国人の自主性に任せっきりにせず、ぜひ、職場全体で機会を設けて外国人の日本語力向上に力を貸してあげてほしいと思います。
日本が目指すべき共生社会において、やはり言語はその基礎となります。「郷に入っては郷に従え」というのではなく、外国人が社会に馴染むための手助けをしてあげることで、外国人労働者のモチベーションが向上し、その結果、しっかりとした日本語能力が身に着けば、「母国語」によらずに支援を遂行することが可能となり、雇用主側にもメリットが生まれます。
特定技能外国人の雇用・採用のご相談はお気軽に!
当事務所は、特定技能を含む外国人雇用を検討中の会社様から、制度や手続きについてのご相談をお受けしております。
出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士が対応いたますので、在留資格(ビザ)申請のお手続きもワンストップで承ることができます。
行政書士山賀からのご挨拶

私は、大学留学を機に渡英し、ロンドンでの就職を経て、スコットランドで宿泊業を開業して、約20年間をイギリスで生活しておりました。自国の文化や生活習慣、言語の異なる環境で、「外国人」として暮らすことの不便さ、不安、困難を痛感する毎日でした。
そのため、日本に帰国してからは、自身の経験から、日本で生活する外国人をはじめとする、いわゆるマイノリティと言われる方達が安心して暮らせるお手伝いをしたいと、行政書士となり当事務所を開設しました。
ひと昔前にはきき慣れなかった、「多様性」、「ダイバーシティ」、「インクルーシブ」といった共生社会を表現する言葉が当たり前のように使われる時代となりました。しかしながら、言葉にして強調しなければならない現状というのは、このような概念がまだ当たり前となっていない社会であることの裏返しであり、本当の共生社会に向けて、外国人雇用を検討する事業者、国際結婚などで日本国籍以外の家族を持つ方々、様々な事情から日本で生活する外国人の皆様のお役に立てれば幸いです。
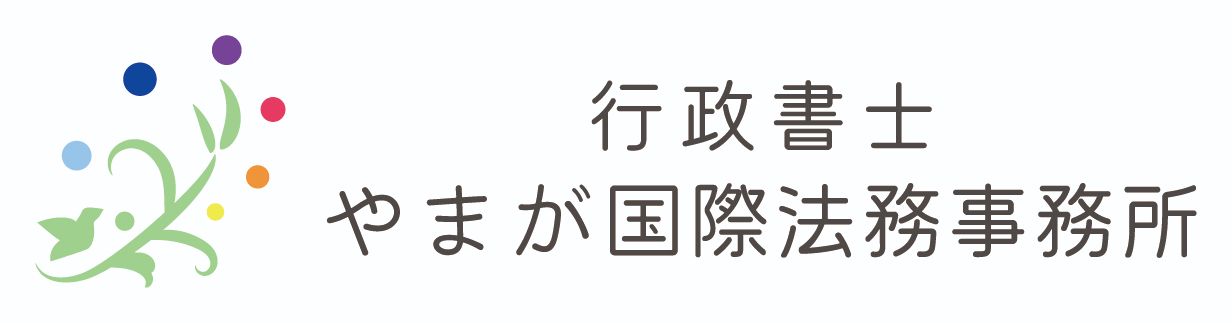








コメント