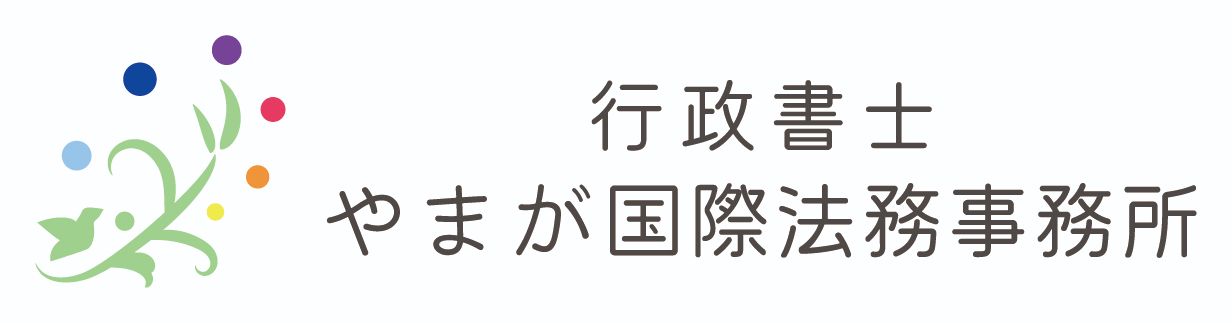1号特定技能外国人の支援担当者は、バイリンガルでないと務まらないのでしょうか

特定技能制度における支援と使用言語
特定技能制度において、1号特定技能外国人の就労や生活をサポートする支援担当者を選任することが必須となっています。
支援担当者は、雇用主である特定技能所属機関の職員の場合もあれば、登録支援機関の職員の場合もあります。登録支援機関は、支援が可能な言語をあらかじめ入管庁に届け出ていますので、特定技能外国人の受入を決定した事業者が、支援のすべてを登録支援機関に委託することを決定した場合、雇用予定の特定技能外国人の母国語で支援が可能な登録支援機関に支援業務を委託しますので言語について悩むことはあまりないでしょう。
一方で、登録支援機関に支援業務を委託せず、自社支援を予定している企業もいらっしゃいます。その場合、特定技能外国人の母国語を話せる職員でないと、自社支援が認められないのでしょうか。
本記事では、特定技能外国人を支援する際に求められる「特定技能外国人が十分に理解できる言語」について、詳しく解説します。
「特定技能外国人が十分に理解できる言語」とは
1号特定技能になるには、JLPT N4レベルの日本語能力が求められます。N4レベルというのは、「基本的な語学力」ですから、「日常生活のなかで身近な話題であれば理解できる」という程度なので、このレベルの日本語力では、複雑な会話は困難ですから、「十分に理解できる言語」とは言えません。
なお、特定技能外国人がN2に合格していれば、「十分に理解できる」と評価することが可能で、日本語のみで支援することが許容される運用です。
しかし、N2レベルの日本語力を持つ特定技能外国人は少なく、やはり、特定技能外国人の母国語や、母国で共通言語として使用されている言語で支援する体制がないと、ビザが許可されません。
自社の職員が話せる言語は日本語のみ。やはり、登録支援機関に支援業務を委託するべきか
自社の職員の中に、特定技能外国人の母国語や十分に理解できる言語を話せる人がいれば、その方に支援担当者になってもらえば話は早いですが、英語くらいならまだしも、特定技能に多いベトナム語やミャンマー語を話せる職員を持つ企業はめったにないのではないでしょうか。
そのような状況であれば、登録支援機関に支援業務を委託するしかないのか、と諦める必要はありません。なぜならば、まず、日常の支援であれば、「翻訳機」を使用して意思疎通を図ることでも、「十分に理解できる言語」による支援として認められ得ます。そして、苦情があるなど、込み入った話をするときには、外部委託の通訳人を用意して相談業務にあたることで、円滑なコミュニケーションが図られますので、いざというときに通訳を依頼できる体制が整っていれば、特定技能外国人を支援することができるものと判断される運用となっています(地方入管によって判断が異なる可能性があるため、所属機関や特定技能外国人の所在地を管轄する地方出入国管理局へ問い合わせて確認することをお勧めします)。
特定技能外国人の日本語レベルアップを支援
いくら、翻訳機や必要な時だけ通訳者を手配すれば済むからといって、特定技能外国人との会話を、特定技能外国人が不自由なく使える言語でずっと行うことは、特定技能外国人の日本語レベルを向上する機会の逸失となってしまいます。
特定技能外国人は、日本で生活し、就労しているのですから、ぜひとも、日本語を上達させて、地域社会にもなじんでもらいたいものです。また、特定技能2号の技能評価試験では、高度な日本語力が求められます。上限5年間の間に、N4からN3またはN2くらいの日本語力を習得できるように、支援担当者は、積極的に日本語学習機会の提供に努めることが望ましいでしょう。